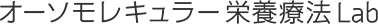闇に葬られる研究とオーソモレキュラー療法の関係
松橋通生教授(東京大学名誉教授、理学博士)は、炭素の生物作用の研究を行いました。
恒温器内において寒天培地に好炭素菌を散布し数日間置くと培地上にコロニーを形成します。ただし、培地に KCl(塩化カリウム)の1%溶液を加えたストレス培地ではコロニーはできません。シャーレに張ったストレス培地の片側半分に炭の粉をまくとそこだけコロニーができますが、残り半分ではコロニーはできません。驚くべきことに、この現象は炭の粉が直接細菌に接していなくても起きるのです。たとえば、炭素をポリエチレンの袋に入れてストレス培地上に置くと炭素の入った袋の周囲からコロニーが形成されていくのです。しかし、シャーレをブリキの箱の中に置いたり、アルミ箔で覆ってしまうとこの現象は観察されないのです。
松橋教授はこの現象を「生物細胞の音波、バイオソニック」と名付け、次のような仮説を国際的な学術誌に報告しました。
炭素の生物作用一炭素の波動から細胞音波へ
「生命を持たない炭素という物質が、何らかの外部エネルギー(たとえば太陽からの赤外線照射)を受けて、これを細菌の増殖シグナルに変えているのではないか」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tanso1949/1998/184/1998_184_213/_pdf
しかし、松橋教授のこの研究を待っていたのは、世界中の研究者からの冷笑や完全な無視でした。冷笑した研究者は、彼ら自身がそうした現象に対する仮説を提唱したわけでもなく、ただ冷笑するだけでした。建設的な議論も起こらないまま、この研究は空中に放り出されてしまいました。以後、この研究をさらに進めるような革新的な研究者は現れませんでした。
ルイ・ケルヴランの原子転換説
同じように闇に葬られた研究に、フランスの科学者、ルイ・ケルヴランの「原子転換」説があります。ここにとても興味深い実験があります。
鶏にカルシウムを全く含まない飼料を与えると、その鶏は殻のない卵を産みます。卵の殻は炭酸カルシウムが主成分なので、その餌にカルシウムが含まれていなければ当然の結果ですね。しかし、飼料のなかに「ケイ素」をいれると、しっかりとした殻のついた卵を産みます。殻の成分はもちろん炭酸カルシウムです。

「鶏の体内でケイ素がカルシウムに原子転換される現象が起こったのです。もっとはっきり言うと、”常温核融合”が起こったのです!」というのがケルヴラン博士の唱えた仮説です。
これまでの常識を覆すような仮説ですが、ケルヴラン博士は1975年にはノーベル化学賞の候補にあがったほどの偉大な科学者ですから、素人の売名行為などではありません。しかし、常識からかけ離れているということで、主流派からは完全に黙殺されました。この仮説が証明されればノーベル賞は間違いなかったはですが、博士の没後10年経った1993年には、屈辱的なイグ・ノーベル賞(「人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究」に対して与えられるノーベル賞のパロディー)を授与されてしまいました。
主流派は、彼を完全に馬鹿にし倒したのです。ここまでやるなら当然、「カルシウムを与えられていない鶏が産む卵の殻のカルシウムがどこから来たのか」について立派な説明があるのかと思いましたが、主流派の学者にはケルヴラン博士の原子転換説に変わる有望な仮説はありませんでした。結局、この現象について現代科学ではいまだに謎とされたままです。反対派の学者たちは、相手の理屈を潰すことに躍起になり、相手を理解し人類にとって大きな価値があるかもしれない発見を一緒に証明しようという真摯な姿勢を端から持ち合わせていないのです。”常識”という既存の理論を金科玉条のごとく盲信し、自分たちの考えと違う新説に対して、異様に攻撃的になるようです。自分が習ってきた教育と違う!ということで、ある種の裏切りを感じ、それで感情的になるのかもしれません。
オーソモレキュラー療法の境遇
中村先生は、こうした埋もれた研究にとても魅力を感じるそうなのですが、それは先生自身が「この道を進もう」と決心したオーソモレキュラー栄養療法も同じような境遇にあるからかもしれません。医学部では、栄養についてはほとんど学びません。現代の医師にはビタミンやミネラルの知識がないのです。自分が習ってこなかった得体の知れない知識への恐怖心からか、オーソモレキュラー栄養療法は医学会の主流派から完全に無視されているのです。
炭の話に戻ると、炭素の性質については未解明なことがまだまだ多いです。しかし、すでに炭は医療の現場で実際に用いられています。たとえば救急医療の現場で、自殺しようとして農薬を大量に飲んだ人が運ばれてくることは珍しくはないのですが、この場合の処置としては、まず胃洗浄を行い併せて活性炭の胃内投与も行います。これは、日本救急医学会に推奨された治療法です。日本中毒学会も活性炭の効用を認めています。
民間療法ということになるのでしょうが、「炭を食べて持病のアトピー性皮膚炎を治した患者さん」の症例報告を見たことがあります。炭がどういう作用を発揮して症状の軽快につながったのかはわかりません。炭の持つ有害物質排出作用によって、水銀などの重金属が排泄されたおかげなのでしょうか。あるいは、炭がそれ独自の波動を放ち、それが腸内細菌の生育に好影響を与えたのでしょうか。
症状改善の作用機序がどうであれ、そもそも主流派医学はこういう報告(現実に起きた事象)を決して認めないのです。そして、ガイドラインという学会公認のお墨付きのもとで次のようなでたらめが治療として堂々とまかり通っているのが現代医療の現場です。
ステロイドの処方という薬害をいまだに標準医療とする学会と皮膚科医師たち。それを正しい治療法だと信じて医師の言いつけを律儀に守っている患者さんを見ると本当に胸が痛みます。経皮吸収されたステロイドは体内に長くとどまり、酸化ステロイドとなって活性酸素を生み出す原因となます。そして、細胞内ではその影響でミトコンドリアがひどいダメージを受けることになるのです。皮膚のかゆみという当初の症状は、そもそも放置すれば自然軽快しているはずのものだったのに、ステロイドを塗ったがために症状を不必要に遷延させ、むしろ悪化させるのです。
ステロイドについては、インターネットや書籍でもその副作用の危険性が広く知れ渡っています。それでも、皮膚科においては相変わらず当たり前のようにステロイドが処方されており、それは子どもが対象でも例外ではありません。現在もアトピー性皮膚炎は増加傾向にあり、食物と環境がその原因とされていますが、症状を抑えるのではなく、治療の第一義を根本原因へのアプローチにしないことにはこの傾向が収まることはないのかもしれません。
「死ぬわけでもあるまいし、所詮ただの皮膚病じゃないか。」
皮膚病で死ぬことはないかもしれません。しかし、「みにくい皮膚で生きていくことは、死ぬより辛いのです。」アトピー性皮膚炎を患っていた中村先生ご自身の体験は患者さんの切実な思いを代弁しているのではないでしょうか。