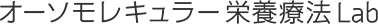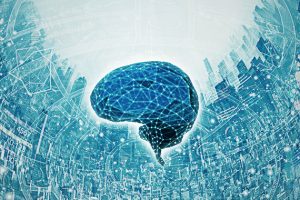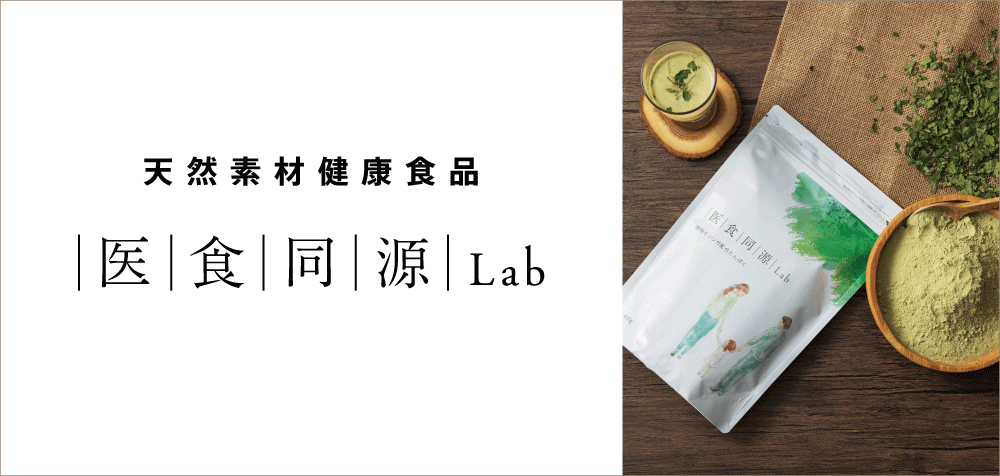硬いだけでは骨折しやすくなる⁉︎
人間の骨格構造の大部分を占める「骨」。
成分としての構造比率は約70%の骨塩と約30%の骨基質からなります。
骨塩:カルシウムやリンなどの無機塩類の総称
骨基質:無機質と主な成分はコラーゲンで作られる硬い組織
骨は硬いだけでは折れてしまいます。
日本にもあちこちに生えている竹を思い出して見てください。
強い風や雨がきても大きく「しなる」ことで衝撃を吸収し折れることなくその状態を保ち、さらに強度のある硬さも兼ね備えています。
乾いた木もパキッと折れやすいですが、木の線維に十分な水分や栄養がある木はしなることで折れにくくなっていると思います。
骨を作る物質はカルシウムのみでなくコラーゲンも重要であり、コラーゲンが弾力を与えそこにカルシウム塩が沈着して硬度を与えています。
子どもの骨に粘りがあり骨折しにくく老人の骨がもろく骨折しやすい特徴をもつのは、一般に加齢と共に有機質(コラーゲン)が減少し無機質(カルシウム)が多くからとも言われています。
ビタミンCはコラーゲンの主要な成分であるアミノ酸の合成に必須になります。
ビタミンCが不足することにより弾力性が失われ適度に「しなる」ことができず硬いだけの骨は折れやすくなってしまいます。
壊血病とビタミンCと骨
「ビタミンC健康法」アーウィン・ストーン著(1974年)に記されている壊血病患者の骨の状態がこう記されています。
「骨は非常にもろくなり、ベッドの上で動いただけで足の骨が折れてしまうこともある。関節がガタガタになり、患者を動かすと、骨がこすれあって、カタカタいう音が聞こえるようになる」
壊血病(かいけつびょう)とはビタミンCの欠乏状態が数週間から数ヶ月続き、出血性の障害が体内の各器官で生じる病気です。
ビタミンCの体内のタンパク質を構成するアミノ酸の1つヒドロキシプロリン(コラーゲンの主要な成分)の合成に必須になります。
ビタミンCが欠乏することによって組織間をつなぐコラーゲンの働きが不十分になる、骨間の生成や保持ができにくくなる、創傷治癒が遅れる、疲れやすい、感染への抵抗力の減少、筋肉や関節の鈍痛など様々な症状が出現してきます。
ビタミンCが化学名でアスコルビン酸(ascorbic acid)と呼ばれるのは、欠乏による壊血病を防ぐ酸「抗(anti-)壊血病の(scorbutic)酸(acid)」に由来しているとされています。
ビタミンCの不足が骨の状態に大きく影響を及ぼすのがわかると思います。
ビタミンCの適切な摂取量は「個人差がある」
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」において厚生労働省がビタミンCの最低食事摂取基準は、成人(15歳以上)における推奨量が100ミリグラムと定めていて壊血病を予防する量としての基準で摂取量を設定しているようです。
『体内で一番濃度変化が激しいビタミン』
ビタミンCはビタミンの中でも、人によって、状況によって、体調によって需要量が大きく変わると言われています。
その要因としては
・吸収されやすく、排泄されやすい
・体調の状態で腸の吸収が異なる
・臓器や細胞の器官において必要な栄養素の量が圴一ではない
上記の理由でビタミンCの適切な摂取量には「個人差」があります。
摂るポイントとしては血中のビタミンC濃度を常に高くしておくことが、臓器や細胞器官へのビタミンCの供給や体調よって変化にも対応することができます。
特に体調が悪い時や風邪をひいた際などにはより効果的だと思われます。
「ビタミンCの血中濃度は、ビタミンCを1g摂ると上昇しますが、4時間後には元に戻ってしまいます。したがって4時間以内にビタミンCを摂れば、血中濃度を高く保つことができるというわけです。」
「ビタミンCは頻回摂取で、下痢になる手前の量(お腹がゴロゴロし始めるくらい)が最適量です。」
医者が教える「あなたのサプリが効かない理由」 著者:宮澤賢史(医師、医学博士、臨床分子栄養学研究会理事長)
体の状態や自分の今の状況を踏まえてビタミンCを摂る量や時間を決めることができるのが理想の1つだと思います。
ヒトが動くために必要不可欠な「骨」を年齢を重ねても強く、硬く、しなやかに維持するためには自分自身に必要な摂取量と時間の『ビタミンC』を把握することが重要になります。
「現代科学の父」と呼ばれノーベル化学賞の授賞経験を持つビタミンC研究で有名なライナス・ポーリング博士は、数ある著書の中でビタミンCの作用は50以上を超えると書いています。
一度、ご自身のビタミンC耐用量を確認して摂り続けてみてください。
これまでの体とは骨格レベルからの違う「しなやかさ」を感じることができるかもしれません。